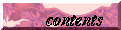『祭囃子』

第二章「秋祭り」
№7
「あら、いたの」
夕子は冬馬を確認すると、本当に冷たく云い放つ。
「夕子、そりゃないだろ。これでも俺は夕子の恋人でしょ」
「えぇ──────────────────?!」
と当然驚く宮子が大きな悲鳴で反論してる。
「まぁ、冬馬が口説き落としたって云うか、泣き落としたって云うか。な。夕子」
「煩いわね。誰にも迷惑掛けてないわよ」
と若干照れている夕子を見るのは、ちょっと嬉しい。
「そうそう迷惑かけてないどころか、迷惑かけるだけ逢ってないしな」
と今度は冬馬の逆襲だった。
(けっ!ザマ見ろ)
「そんなことないわ。今日、こうして逢えたしね」
口では何だかんだ云いつつも、夕子は冬馬の許に行く。二人だけの世界に入った様を見慣れている俺とは違い、目が点になっている宮子はすっかり言葉を失っていた。
そんな宮子を見ているのも結構可愛くていいかもな。
二人を見ると冬馬が少し夕子を責めていた。
「そうだね、かれこれ一ヶ月逢ってなかったけれどね」
「ごめ~ん」
その時、俺と宮子の存在は二人の頭の中から完全に抹消されたようである。二人は手を取り合って夕子の部屋へと消えていった。残された俺たちが思わず笑ってしまうのは仕方のないことだろう。
冬馬。
左近冬馬。
保育園の時からの腐れ縁。俺が所謂“私生児”で、その事でよく苛められてたのをいっつも助けてくれた。小学校から中学、そして高校まで、あいつは同じ学校を選びいつしか親友だと呼べる相手になった。
夕子のことは初恋で、高三の時、とうとう玉砕覚悟で口説き落とした。一番凄いと思ったのは冬馬の両親。夕子が困り果てて相談に行くと逆に「頼む」と頭を下げられた。
来年春、あと半年もすると二人は結婚する予定になっている。
そして親友が父親になる。
夕子を「お母さん」と呼ばないように、冬馬を「お父さん」と呼ぶことは一生ないだろう。
でも心の中では何時も「お母さん」だったように、冬馬は「父」だ。助け合う、親友の父だ。そんな奴が夕子を選んでくれて、俺は嬉しい。
自分の部屋へ宮子を通すと他愛もないことをずっと話していた。眠るのが勿体無いくらいだ。
それでも明け方になり、宮子がうつらうつらし始めるとベッドを彼女に明け渡し、俺はリビングに戻ってきた。
「光。明日、秋祭りどうする?」
すると思いがけず、冬馬の声が迎えてくれた。
「何、早いじゃん」
時計をみると午前六時。
「今夕子が出掛けたとこ。寝ようかとも思ったんだけど、光のことだから起きてくるかなと思ってさ」
そう云うと冬馬は左の眉を上げる。
「そりゃ、よいご判断で」
「もしかして徹夜か?」
「うん。宮子もさっき眠ったとこ」
「話は大体聞いた。よかったな、手遅れにならなくて」
冬馬はお盆にあるポットからお湯を注ぎ、コーヒーを入れている。
「冬馬のお蔭だ。逃げ出してこいって誘ってくれたから再会できたんだ。本当に有難う」
心からそう思った。
「落ち込んで勉強も手につかないなら思いっきり飲もう」
と誘ってくれた。
冬馬は少し照れたように笑みを浮かべ無造作にコーヒーカップを差し出し、俺はそれを受け取り小さく「サンキュ」と云う。
「で、祭りは?」
「行くよ。そのために、この日に合わせて帰ってきたようなもんさ」
「そっか。綺麗だよ。落葉の絨毯。今年の紅葉はホントに綺麗だ。明日、夕子とデートするんだ。邪魔すんなよ」
「お互い様だ」
二人は顔を見合わせて、どちらからともなく笑いだした。