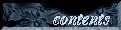『祭囃子』

第一章「冬祭り」
№2
「目が覚めた?」
私は、うっすらと目を開いた青年に向かって小さな声で問いかける。彼は反射的に私の方へ振り向いた──。
たっぷりと悩んだ後で、
「誰ですか?」
と彼は聞いてきた。最もだ。
しかし!
「それは私が聞きたい。身分証明出来る物が何もなくて、病院の人が困っていたわ」
私がそう云うと、彼は辺りを見渡している。
「そっか。かばんを持っていなかったんだ。ごめんなさい。ところで僕は一体どうしたんでしょう?」
にやり。私の顔には正にこの言葉にピッタリの笑みが浮かんだだろう。
(もらった!)
と思った私はすかさず立ち上がり、あのブレザーを若干オーバーアクション気味に羽織った。
「何だ!? それ!!」
勿論、そう云うだろうと思ってた。
「君の血だよ」
私がさり気なくそう云うと彼の悪い顔色から更に血の気が引いてゆく。流石に絶句していた──。
そうでしょうとも。半分以上‥否、大半が真っ赤に醜く染まり、今はそれが乾き始め黒く変色しようとするところだった血の痕。
(ちょっと気持ちよい〜)
ふと視線を感じ彼に目をやると、その極上の顔をした彼が不思議そうな表情を浮かべ私を見ている。
軽く咳払いをして私が姿勢を整えると、突然彼が起き上がろうとする。
「わぁ、起きるな!! 点滴中よ」
私は慌てて針の入っている左の腕を押さえつけた。
「あ、あれっ、ごめんなさい」
「外れてない!? 大丈夫…よかった」
私は折りたたみ椅子に腰を掛け、ほ〜っと一息入れる。
「ごめんなさい。意地悪してるのと同じね。でも、ここまで見事に染まった物を持ち主としては是非披露したい。決して怒っているわけじゃないから気にしないで」
「でも…弁償します。否、すぐには無理かもしれないけれど、出来れば分割でお願いしてもいいですか?」
病院のベッドで青白い顔をして点滴を受ける青年の顔。
この時。私は、もしかしたら見た目と違って彼はもっと素朴なむしろ少年に近い純粋な子かもしれない、と思った。
「気にしなくていい、と云った筈よ。今の言葉だけで充分よ」
本当にそう思った。弁償してもらおうなんて考えてもみなかった。やっぱり“おぼっちゃま”なのかしらね。
「こんな姿勢で失礼します。僕、山科光人(やましなみつひと)と云います。関東芸大の三回生です」
とベッドに横たわったままの彼。
「私は村崎夕子(むらさきゆうこ)。インテリアデザイナーしてます…って言葉の意味が解る?」
「あ〜雑誌に載ってましたよね。見たことある顔だと思いました」
私は、かなり派手に驚いた。
「よく知ってるわね。あれは友人に頼まれただけ。私の実力じゃまだまだ」
「でも表参道のラインってブティック、僕は好きです」
「!!」
私は声にならぬ声を吐き出した。
この戦後十数年の混乱期、よく一男子大学生が“ブティック”なんて言葉を知っていたことか。更にラインを知っているとは、この子一体何者なの!?
私が余程、疑惑の眼差しを向けたのであろう。
「専攻がデザイン科なんです。ラインは父の友人が経営する店で、勿論身内贔屓で褒めたわけではありませんが、他の店は当然知りません」
と彼の方から話し始めた。
「成程ね。それで詳しいわけだ」
「雑誌も店にあったんです。店主が“これからこの世界は変わる”ってタイトルが気にいって、お客さんに見せていました」
「どちらにしろ、君はいいとこのおぼっちゃまってことね。ラインは大半が外国人相手の店よ。例え父親が友人だからといって簡単に出入り出来る店ではないわ」
そう私が云うと、彼の表情は俄かに曇った。
「どうしたの?」
「いえ。確かにそうかもしれません。分不相応な暮らしは僕には重過ぎる」
何を甘えているのだろうと思っていると、
「だからといって、弁償を親に頼んだりはしません。必ず僕が何とかします」
と云う。
おかしな子。思わず笑ってしまった。すると彼もまた微笑んでいる。
「自宅はあの辺りなの? 救急車の都合でこの病院に来ることになってしまったけれど、あの場所からだと少し遠いわよ。どちらにしろ今夜は泊まりだって。家族に連絡しましょうか?」
「いいえ。地方出身なんで家には知らせません」
「そうは云っても、いろいろと不便でしょ」
そう云う私に、彼は再びにっこりと微笑んだ。全く世間を知らないんだろうか。
「じゃ率直に云おう。お金あるの?」
「え…」
「悪い事は云わない。とにかく連絡しなさい。請求書は容赦なくやってくるわよ」
彼は私の言葉で現実を知っただろう。空いている右手の指を口元に持っていき暫し考えこんでいた。
「いくらくらいかかるでしょうか? 少しならバイトで貯めた分もあるし、仕送りをやり繰りすれば何とかなるでしょうか」
「仕送りの額にもよると思うけれど、何千円で済むとは思えない──」
私は少し冷たく話した。ここで優しい言葉をかけ「何とかなる」と話したところで後から「話しが違う」と云われても困るし、医師の話ではそれはないように思われた。
彼は暫く入院することになるだろう。一日で済む話ではないのだ。私がそのことを告げると本当に困った顔をしていた。
何故だろう。ここまで話して私は彼が本当に自分の力で何とかしようとしているような気がしてきた。直感だ。否、単に騙されているだけかもしれないが‥
「事情を聞いてみようか?」
「えっ!?」
「このご時世、親を頼らず生きるって威張っているガキ共は山程いるけれど本当のところ頼っているわけよ。でも君の場合、本当に一人で何とかしたいみたい。今時、私みたいに仕事をする女はツマはじき。でも少しは世の中の役にも立ちたいじゃない。ここはドンッとこの夕子姉さんに話してごらん」
彼は横になったまま私の顔をじっと見上げていた。何だか彼の視線に居たたまれなくなり、私は落ちている点滴の滴に視線を移す。
本当に綺麗な子よね。目のやり場に困るわ。
「母親が…」
「えっ?」
唐突に彼が口を開いた。
「母親が、去年赤ん坊を産んだばっかりなんです。再婚して初めての子で。新しい義父にも男女一人ずついて、こっちに僕がいて、今度が四人目です。お金の為に再婚したようなもんです。一人じゃ僕を育てられないからって。義父も分かってくれていて僕は大学からこっちで暮らしています。義父が小さな家を買ってくれて家賃と学費の心配がないから余りバイトもしたことがなくて、正直ここの支払いで足りるのか不安です。でも母には迷惑をかけたくない」
光人は顔を背けた。
何がそんなに辛いんだろう。この美しい顔が歪むなんて、私は許せない。
「家って、いいとこ?」
「ええ多分」
「ねぇ私、今のアパート来月出なくちゃならないの。君の家に居候させてくれないかなぁ。その代わりお金を立て替える。掃除、洗濯、料理も、あと看病も出来る範囲でやるから」
「何云ってるんですか?」
「暫くは安静にして寝てなくちゃ。お母さんが駄目なら他に誰がやるの? 恋人でもいるの?」
「いいえ」
「そうよね。だから私」
と人指し指を鼻先に向ける。
「どうして部屋を出されるんですか?」
「痛いところを突いてくるわね。元々そういう契約だったの。来月部屋の持ち主が急に長期出張から戻ることになったらしくて、突然の話だったから正直に云うとちょっと途方に暮れていたの」
よくぞここまで立て板に水という具合に嘘がつけたものだ。眠れる才能か、はたまた本物の魔女か。自分でも空恐ろしいものを感じざるを得ない。
しかし、それを知ってか知らずか、
「分かりました。そういうことならお言葉に甘えて面倒を見て下さい。じゃ今度は村崎さんのことも教えて下さい。逆の立場になった時僕が叱られちゃう」
…何故か笑ってしまった。苦笑いってヤツだ。
「ごめん、ごめん。私、そんな風に気遣ってもらうことなんて今まで全然なかったから、どう云っていいのか、ちょっと分からなくて‥つい‥あれ!?」
何故だろう‥。知らないうちに涙が止まらなくなっている。
「村崎さん‥。夕子さんって呼んでもいいですか?」
私は返事をする事が出来ず、首を二度縦に振る。
「夕子さんも寂しい人なんですね」
私はその言葉に少しだけ驚いて、しゃくりあげながら聞いてみる。
「も、って何? なら君も寂しい人だっていうの?」
すると彼は首を横に振り、
「僕じゃなくて母です。よくそんな感じで泣いていたから」
「そんな、感じって?」
「ん〜上手く云えないですが、テレ隠しみたいに何かを誤魔化しながら泣くんです。みっともないところを見られたって感じに。でも真実は凄く寂しさを抱えている気がしてました」
私は言葉が出なかった。何故なら、正にその通りだったから。彼の言葉から逃れるように私は彼に背を向け窓際に立った。
窓の外には、いつしか梅雨空が戻ってきている。間もなく雨が落ち始めるだろう。遠くに見える木々の葉が風に揺れるのを見ながら、私は静かに泣き続けた。
戦災孤児は何も私一人ではない。何処のどんな子も、みんな心が飢えているのは同じだった。だからこそ今まで誰にもそんな心の奥底を見破られたりなんかしなかった。それがいとも簡単に目の前の青年は見破った、ということに少なからず驚いていた。
そしてひとしきり泣いた後、顔を上げ振り返った──。
彼の微笑んだ顔をそこに見た時、私ははっきりと感じ取っていた。今後の彼の人生に深く関わっていくことになるだろう、と。
きっと長い時間をかけて、ずっと、ずうっと…。
数日後、私は彼の自宅へ転がり込み共同生活が始まった。家は平屋で使っていないという一部屋を提供してもらい荷物を入れ、普段は彼が主にいる居間に居た。確かにこの東京に一軒家。どんな状態であれここに一人暮らしは贅沢だろう。
退院して半月程は布団から起き上がることも出来なかったけれど、一月もすると彼は再び通学し始めた。
いつ追い出されてもおかしくはなかったのに、彼は私をずっと傍に置いてくれた‥。
それまでに感じたことのない暖かい空気に包まれて、彼が何も云わないのをいい事にずうずうしくもずっと居座り続けていた。
暮らしが次第に居候から住人に変わりつつあると思うのは、私の独りよがりだろうか‥