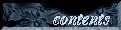『祭囃子』

第一章「冬祭り」
№4
「ね。もう、いいよね。本当の病名、教えてくれよ」
殺風景な病室に静かに横たわる光人は、毎日同じ質問を繰り返す。その表情は穏やかで、だから私もその度に同じ答えを繰り返す。
「貧血だって。私の料理の腕をけなされたようで、ちょっと悲しかったわ‥」
あの料理が拙かったのか、それとも、あの献立が合わなかったのか、と日々少しずつアレンジして光人に愚痴を云う。すると光人は、
「仕方がないな〜」
と呟きながら力なく笑ってくれる。本当のことなんて私は知らない。今、目の前にいる光人が全てだ。
私には何も云えなかった。
入院して一ヶ月、光人の実家からは何の連絡もなく上京する者もいなかった。
入院してすぐ、電話をした時に話を聞いてくれた人は誰だったのだろう。「頼む頼む」とそればかりで、母親くらいは駆けつけてもよさそうなものなのに。
でも光人はそれを分かっているのか、一度も両親のことを尋ねてくることはない。それが尚更、胸に影を落とし一層愁いに沈んだ。
「光人、散歩しようか」
とある小春日和の昼下がり。私は光人に声を掛けた。
「そうだな」
「じゃ車椅子を借りてくる」
病室の重苦しい空気から逃げ出したくて、私は廊下に出た。看護婦が忙しそうに走り回っている。すっかり顔見知りになった婦長を捉まえると、外に出てもいいかという確認と車椅子の件を話す。
「比較的落ち着いているからいいでしょう」
と許しを貰い私たちは病院の庭に出た。
「すっかり冬景色だな」
一月前も充分“冬”だったのに一体何がどう違うのだろう。それでも確かに光人の云う通り、私にも何かが違って見える。
「何だか淋しいな」
「そう? でも来週、向こうの通りで冬祭りがあるんですって。先生に話して出かけてみない?」
「冬祭り?! へぇ〜面白そうだから行ってみようか」
「うん!!」
私は力一杯返事をした。
「そんなに嬉しい?」
車椅子から体を起こすように、私の顔を覗きこむ。
「勿論。何せ初めてのデートだからね」
そう云うと、光人がいつになく大きな声で笑った──。
翌週、私たちは担当の医師から許可をもらい、予定通り冬祭りに出掛けることとなった。
お互い口には出さなくとも、多分これが最後の外出になるだろうことを薄々感じ知っている。
それでも祭りはいい。夏だろうが冬だろうが、祭りといえば屋台。それは変わらない。せいぜい女の子の服装が、浴衣から着物になるくらいだ。数多くの屋台が所狭しと並び、男たちの大きな声が飛びかう。
「楽しそうだな」
この日、車椅子は要らないと云った光人は、ゆっくりではあるがそれでも杖をつきながら自分の足で歩いた。歩いては休み、休んではまた歩く。少し離れたところに見つけた小さなベンチに腰を下ろし光人が空を見上げた。
「病気になって、いい事もあった」
「そう?」
「何でもない事が、本当は大事だってことに気がついた」
そう云う光人の視線が私に向いたことに気付きながらも、私は走り回る子供たちから目が離せずにいた、耳だけを光人に傾けて。
「そうね。私も人に対して優しくなったわ。健康が如何に大事かということも、知っているようで知らなかった」
「夕子、怒るなよ」
そう云って、光人は私の手を握る。
「俺さ。死にたかった。病気になるずっと前から病気が判った瞬間まで、早く死にたいって毎日そればっかり考えてた。でも夕子に出逢って一緒に暮らして…楽しかった。夕子のこと好きになって初めて生きていたいと思った。今までの罰が当たったのかな、こんな病気になるなんて。病気にならなきゃ逢えなかった夕子に別の何処かで巡り逢いたかった」
その時、社の奥にある庭園から一斉に鳩が飛び立った。同じ動きをする、その鳩の群れをひとしきり目で追うと群れは再び庭園に降りてゆく。
「それでも夕子が近くにいてくれたから、俺は倖せだ」
光人の言葉はその手を通し心に沁み込んでくる。
「私も。戦争で何もかも失って何をしていても楽しくなかった。どんなに最先端の仕事と云われても、日本じゃまだ受け入れてもらえない。私は偶然巡り合った人が外国で仕事をしてる人で、知らないうちにどんどん仕事が増えたけれど日本を離れる決心はなかなかつかなかった。そんな時だった、光人と出逢ったのは。それまでとは全く違う空気だと思った。目が覚めたように、ぱぁっと世界が広がったの」
私は繋いだ手に力を籠める。そしてゆっくりと光人の瞳を見た。
「誰かの為に生きることが、こんなに充実してるなんて知らなかった。私も倖せ。毎日貴方と一緒にいられるだけでもう他には何も要らない」