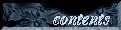『祭囃子』

第三章「春祭り」
№15
「会ってしまったな、ついに」
そこは小さなビジネスホテルだ。豪華なソファがあるわけでもなく、親父には机とSETになった椅子を勧め俺はベッドに腰をかける。小さな窓のカーテンを開けると、遠くの山が桜に染まっていた。
何から話せばいいものか、流石に言葉に詰まっていると親父の方から先に言葉が出る。
「それにしても、よく私が判ったな」
「当然だろ。そっちこそ俺が本当に判ったのかよ」
これじゃ喧嘩売ってるみたいだ。
正直、親父が判ってくれたとは思っていない。云ってみれば俺は赤の他人だと思われている相手に抱きつき号泣したのである。
でも、親父はそんな俺を振りほどこうとはしなかった。小さく「宝雪か」という言葉が聞こえ、俺は我に返ったのだった。
聞きたいことは山程あった。いつか親父が帰ってきたら、あれもこれも聞いてやろうと思っていた子供の頃を思い出していた。
しかし、いざ親父を目の前にすると何も言葉が出てこない。どんな親でも親は親。祖母ちゃんの口癖だ。確かにそうだ。生きていてくれたというだけで、もう何もかもがどうでもよくなった。
「今までのこと、何でもいいから話してよ」
「話せることなど何もないよ。日雇いの仕事をして暮らしてる。体だけは丈夫だったから今日までやってこられた」
よく見ると、肌理の細かった肌もかなりくたびれている。
「何処に住んでるの?」
戸籍が使えないんだ。部屋を借りるなんて出来るのか。
「今、世話になってる土建屋さんが昔気質の豪快な社長でね。その人の家の離れに住み込ませてもらってる。昔は私のような奴がゴロゴロいたとかで透明人間を飼っているようなものだと云ってくれてるよ」
そっか。いい人に巡り会っていたんだ。
確かに、土建屋には親父の資格はオイシいだろうが果たして使えるのだろうか。まぁ資格がなくても一級建築士の才能が消えるわけではないだろうけれど。
「さっき、判ったのかと聞いたな」
そう云うと親父は真っ直ぐ俺を見る。
「判ったよ。今のお前は若い頃の私に瓜二つだ。私が死んだ父に瓜二つと云われたように、私たちは長い時間をかけた三つ子のようだ」
昔から似た者親子だった。両親同士が似ていたのだから似ていて当たり前だと思っていたが、死んだ祖父さんなんて話題にも上ったことのない人が出てきてちょっと戸惑った。
「みんな元気にしているか」
と云って、すぐ、
「私が聞いていいことではなかったな」
と嘯いた。それは、まるで聞きたくてたまらないくせに、詰まらない意地を張ってる子供みたいに見えた。
「何でも話すよ。その代わり親父も隠し事しないで全部話して」
暫く考えこんでいる親父。やっぱり話せないから家を出たのだろうか。いつかのお袋の言葉が蘇る。
「今日まで生きていて会った、ということは宝雪に話す為だったのかもしれない。いいだろう、何もかも話すよ」
親父なりに覚悟を決めたということだろうか。ただそうは云ったものの、なかなか先には進まないように見えた。