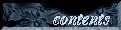『祭囃子』

第三章「春祭り」
№5
「お袋」
「何?」
手を止めることなく、俺を見る。
「父さんのこと、どう思ってる?」
「好きや。今も、今までも、これからも」
一瞬の躊躇いもなく出る言葉。
「突然、理由もなく蒸発しちまうような、そんな男でも?!」
こんなこと云う心算なんてなかったのに、あんまり簡単に「好き」なんて云うから、ちょっと意地悪してみたくなった。
するとお袋が笑った。
「宝雪は父さんがどんな人か、よう解ってへんのよ。光が私の前から姿を消したんは必ず訳がある。中学生になったばかりの宝雪を残していかなならんかった。それが何故か。教えてくれへんかったんは、きっと教えたらあかんかったからや。光が、誰にも見せへん顔を知ってる。誰も知らへん顔を知ってる。どんなに離れていても心は繋がっていると信じてる。それだけで充分や」
ちょっと気恥ずかしいなぁ、と云ってお袋が照れ笑いをした。俺の琴線に何かが触れた。
「待ってるとは云わないのか?」
お袋は、少しだけ首を振り、
「帰ってこないかもしれへんから待ってると辛いやろ。だから待たへん」
と答えた。
強いなぁ。
流石は京女か。いつも云ってたからな、京女を莫迦にすると痛い目に遭うよって。
「なぁ。ホントに何も知らないの? 祖母ちゃんや冬馬おじちゃんとか、何も聞かされてないの?!」
「私には、みんな知らないって云うし。本当か嘘かやあらへん。私は知らへん」
息が詰まりそうだった。一度部屋を出て湯のみを二つ持って戻ってくる。
「遅いからお茶な」
と差し出した。礼を云いお袋が湯のみを受け取り口をつける。
「あんたの淹れるお茶は本当に一級品や。同じお茶の葉やのに何が違うんやろね」
お袋のそんなお褒めの言葉を聞きながら、暫時二人でお茶を飲む。葉の香りなんだろうか。次第に気持ちが落ち着いてきた。
そして俺はかねてから決めていたことを、お袋に告げることにした。
「十年だね。認定受けて区切りをつけよう」
一呼吸、待った。
「宝雪がそれでいいなら」
「俺じゃないでしょ。お袋が父さんの死を受け入れるか、だよ」
「紙切れの上の事や。私は気にしん」
お袋の顔は明るい。きっと内側じゃいろんなものがうごめいているんだろうけれどな。
「よく云った。それでこそ母さんだ。じゃ手続きしよう。祖母ちゃんたちを楽にしてあげなきゃね」
「そうやね」
お袋の瞳から涙がこぼれた。俺は気付かないふりをして静かに部屋を出た。