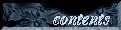『祭囃子』

第一章「冬祭り」
№8
目が覚めた時、暫く笑っていなかったことに気がついた。
何を怖がっていたんだろう。全てを受け止めると決めた時から覚悟は出来ていた筈なのに。ならば最期の時まで笑っていよう。それが一番私らしい。
そう決心して、再び光人のいる集中治療室前の廊下へと私は戻ってきた。
長い時だった。いつもなら考えることすらなく過ぎてゆく時間を一秒一秒心に刻みながら、それでも一秒でも長くと祈る。
「まだ連れて逝かないで」
と。
そんな日が五日程続き、私は医師から入室を許可された。
いよいよ、その時が近づきつつあることを私は痛いほど感じとっていた。
頑丈そうな扉を開けると中は二重扉に仕切られており、いかにも重病人のための病室だということを思い知らされる。多くの危篤患者が様々な運命を辿った空間に私は押し潰されそうだった。
内側の扉を開けてくれた看護婦が私を待っている。重い足を引きずるようにして私は中へと入った。何もない部屋。人を生かす為に置かれた器具だけが規則正しい音を響かせている。異様にも映る真っ白な壁が迫ってくるようにも見えた。
こんな場所で、どんな様子の彼に会うことになるんだろうと恐る恐る視線を奥へと移していく。
ところが通された部屋にあるベッドの上に、光人は起き上がっていた。
「起きていていいの?」
私は驚きと嬉しさがこみ上げてきて、なかなか言葉が続かない。
「今は平気」
光人ははっきりと答えた。すぐにでも駆け寄りたかった。
しかし私の足は近づくことが出来ず、扉を背に立ち尽くしてしまっていた。彼の声音は優しかったのに足がすくんでしまって動かない。
その距離は息遣いが届くほどに近く数歩で着いてしまうのに、私には遥か永遠を思わせた。
「夕子、おいで」
いつまでも歩き出さない私に、何を感じたのであろうか。光人が右手を差し出し、声をかけてくれる。私は、ふらふらと(どちらが病人か、分からないね)彼の許へと近づいていく。
「光人。寂しいよ。早く帰ろう」
「そうだな」
光人は窓のない部屋の中で、遠くを見るように視線を泳がす。凍てついた空気が其処には在った。泣いちゃ駄目だと知りつつも、瞳に溜まる涙はどんどん増えてゆく。
「もう、泣いてもいいよ」
私は彼の胸へと飛び込み、初めて声を上げて泣いた。髪を撫でる光人の手はとても優しく、暖かかった。
「夕子、頼みがある」
「何?」
「俺の代わりに、東京タワーが完成したら見に行って欲しい」
驚いて顔を上げた。
「有難う。夕子のお蔭で幸せだった。人として死ぬことが出来るとは思っていなかったから。本当に有難う。ごめんな」
私は、首を左右に振りながら彼の言葉を聞いた。
「こんなことならもっと早くに夕子を解放してやるべきだったな。でも‥俺は臆病で、‥それが出来なかった。意地を張らないで、京都にも‥行けばよかった。いい所だよ、あの街は。いつか行ったら、‥俺の育った街を見て‥きて。いろんなお祭りもあるし‥、様々な四‥季の‥行事‥も、本当は‥嫌いじゃ‥なかった‥。いも‥うと・・・」
光人の意識が朦朧としてくると、医師が再び彼を寝かせ、
「覚悟をしておいて下さい」
と告げた。私は次第に苦しそうになってゆく光人の手を、握っていることしかできなかった──。
増えていく点滴の量。医師が腕時計に何度も目を落とす。酸素吸入をしていても苦しそうに喘いでいる彼の姿は一体何と闘っているのだろうか。そんな中で彼は何度も私の名を呼んだ。
これだけ愛してくれたら女冥利に尽きるってもんだわ。
そして数分後、彼は二度と私の許へ戻ってくる事はなくなった。
その後、医師から死の直前の彼の様子についての説明があった。
意識が突然戻り、
「夕子を呼んで欲しい」
と云われた時はその場に居合わせた誰もが、うわ言を云っていると思ったという。医師もそれを聞き私を呼ぶように云った後、
「先生、起こして下さい」
という光人の言葉を聞いて初めて、意識が戻っていることを確信したのだと。
「本当に驚きました。人間の愛情の前には詰め込まれた医学の常識など、何の役にも立ちませんでした」
医師はそう云うと小さなボタンを手渡してくれた。
「ずっと握りしめていました。最期まで離さなかった。それは貴女だと。私の見立てる残り一日を棒に振っても、山科さんは貴女と話したかったんでしょうね。彼の精神力には全く叶いません。僕はまた一から勉強のし直しです」
医師は、それでは、と残し去った。
ボタン。
それは最初に出逢った時の、私の上着についていた物だった。
私の気持ちを汲んでくれたのか、雨が静かに降り続く。見上げると、そこに微笑んだ光人が見えるようだった。