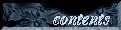『祭囃子』

第三章「春祭り」
№16
「ルームサービスでも取ろうか」
重い空気を断ち切りたくてホテルのしおりを広げる。すると、
「金がない。何も要らないよ」
と、そんな言葉が返ってきた。
「俺が取るの。残った物を食べたって文句云うなよ」
適当に飲み物とサンドウィッチを注文した。夜は外に食べに出ればいい。その場しのぎの言い訳だ。
「親父、俺、高校教師になったよ」
それを聞くと親父の顔が少しだけ明るくなった。
「で、教え子と結婚した」
えっ?! という戸惑いの表情。
ざまあみろ、もっと驚け!
「更に在校中に、式挙げた」
ここまできて、どうやら開き直ったらしい。
「私の子だけあって情熱的だね~」
「一緒にするなよ」
漸く、二人の間に淀んでいた空気が流れ始めた。
届いたコーヒーとサンドウィッチを取り差し出してみる。親父は有難うと受け取ってくれた。それだけのことなのに、ひどく嬉しかった。
「家に帰ろう。お袋が待ってるよ」
静かに、静かに問いかける。
「孫もいるよ。女の子。葵(あをい)っていうんだ。めちゃくちゃ可愛いよ。会いたいだろ。だから一緒に帰ろう、父さんのあの家に」
親父は小さく息を吐くと、首を横に振った。
「どうして?」
「宝雪。お前は男だ。どんなことがあっても家族を守っていかなくちゃならない。ただ、どんなことがあっても知られてはならない秘密を抱えて、生きていけるか?」
何を云いたいのか、皆目見当もつかない。
「何だよ、それ」
「私には出来なかった。余りに可哀想で、私自身が真実ごと消えるのが一番だと思った。要は逃げ出したんだ」
親父の言葉は、もう何年も繰り返し思い継がれていたのだろう。口を挟むことが躊躇われた。
でも何か云わなきゃ押し切られてしまう。
「何、勝手なこと云ってるんだよ。ちゃんと話せよ。それじゃ全然分かんないよ」
「重いぞ。知らない方がいい」
全部話すというわりには、随分はっきりと断定するんだね。
「どうして、いつもそうやって勝手に決めるんだ。母さんに云えないなら云わなくてもいいじゃないか。母さんは無理矢理聞いたりしないだろ。黙っていればいい。帰ろうよ」
「許してくれ。私は帰れない」
「父さん…」
俺は気付かないうちに泣いていたようだ。駄々をこねる子供のように。ただ一緒に帰って欲しかっただけなのに。それを頭から否定されてしまった。
こんなに云っても帰れない理由って一体何だろう。
「じゃ、その訳とやらを聞かせろよ。それに納得することが出来たら、ここで会ったことも誰にも云わない。勿論、もう二度と会わない」
本心ではなかった。でも他に言葉がみつからないのだ。そんな俺をどう見たのか。親父は脱いでいたジャケットを取り、胸ポケットから一通の手紙を取り出した。そして黙ってそれを差し出してくる。
表には何も書かれていなかった。裏を返すと“光”の一文字。
何だろう。親父の書いた手紙か?!
「読んだら二度と忘れられない。でも一切誰かに漏らしてはならない。俺は家族を捨てて逃げた。それでも、お前は読むか?」
何を書いたんだろう。切羽詰まった親父の表情が、何か重大な秘密を窺わせた。
「俺も家族を捨てるっていうの?!」
「それは分からない。お前は私とは違う。ただ苦しむことが分かっているのに親としては知らせたくない」
そうは云うが、何処かで会ったら渡そうと思っていたんだろう。俺の手にある手紙を取り上げることはなかった。
俺は覚悟を決めて、中身を取り出した──。