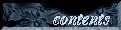『祭囃子』

第三章「春祭り」
№19
あれから一年が過ぎ、俺は冬馬おじちゃんを一人で訪ねた。季節は再び桜満開の春だった。
「今日は一人か。みんなで来ればいいのに。野郎の顔だけなんか見たくないぞ。葵や若菜は元気にしてるか?」
彼の口が悪いのは相変わらずだ。座布団を勧めてくれて、いつもの挨拶のような言葉が降ってくる。
俺が親父に会ったことを話すと、おじちゃんはひどく驚いていた。ただ「どうして連れて帰らなかったんだ」とは云われなかった。その時、やっぱり知っているんだと直感した。
おじちゃんが一度奥に消え、暫くして急須と湯のみを二つお盆に載せ、右手にポットを持って戻ってきた。
「俺が淹れるよ」
おじちゃんは、頼むとお盆をこちらに寄こした。
きっと、おじちゃんの頭の中をいろんなものが右往左往してるんだろうな。黙ってお茶を淹れ、前に置く。
「宝雪の淹れてくれるお茶はいつも美味いな。このお茶が飲めないなんて、光も可哀想な奴だ」
何かのついで、みたいな感じで親父の名前を口にした。
でも多分、これが親父がいなくなってから最初に聞く親父の名前のような気がする。
「おじちゃん」
「何だ」
「あの手紙、読んだ」
おじちゃんが絶句している。そうだろうなぁ。俺もこんな風に話せるまで一年かかったもん。
「もしかすると連絡取り合ってる?」
おじちゃんはすぐには答えず、俺の顔を可なり不躾に見ていた。
「いいや。会ってもいないし、連絡方法も知らない。ただ捜してやりたいと思っていたのは本当だ。夕子のことを教えてやりたくて、でもどうしても見つからなかった」
根っからの東京育ちのおじちゃんは男が泣くなんてみっともないという人間で、今も本当は泣いているくせに花粉症のせいにしてる。
「いちおね、祖母ちゃんのことも話したよ。親父からもいろいろ聞いた。今までずっと有難う。たった一人で耐えてくれて、これからは俺も運命共同体だから。寂しくなったり話したくなったりしたら遠慮なく呼んで。勿論、そういう用でなくても遊びに来るけれどね」
おじちゃんが空を仰ぐ。
「なあ。今、光は何処にいるんだ?」
「知らない」
聞くと、バンッと卓袱台に八つ当たりをするように手を置いて身を乗り出してきた。
「どういうことだ」
「おじちゃんと同じことをしただけだよ。もう“村崎光”は死亡してるんだ。独りで生きていくってさ」
それを聞いて流石に涙腺が壊れたか。便所、と云っておじちゃんは席を立った。