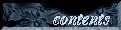『祭囃子』

第三章「春祭り」
№20
暫くして戻ってきたおじちゃんは、数枚の写真を持っていた。誰かが写ったその写真を黙って卓袱台に並べてゆく。思わず覗き込んだ。
「父さん?!」
随分古い写真だったが、若い頃の親父に似ているような気がした。
おじちゃんはすぐには答える気がないようだ。数えると十二枚。そのうち三枚は同じ写真だった。
「これは宝雪の本当の御祖父さんの写真だ」
!!
そんなものが存在してることすら、知らなかった。じゃあ、この人が…
「宝雪。京都の家、憶えてるか?」
おじちゃんが唐突に話を変えた。
「子供の頃に住んでた処のこと? もう殆ど憶えてないけれどアルバムに残っている部分は知ってるよ」
おじちゃんは冷めたお茶を飲み干して、改めて急須から茶を注ぐ。
「あそこは元々光人さん、つまり宝雪の御祖父さんが子供の頃に住んでた家だったんだよ。御祖父さんの父親って人は随分早くに亡くなって、どうしようもなくて手離したんだそうだ。その後家を買った人が事情を知って、御祖父さんが家に来ることを受け入れてくれたそうだよ」
新しく淹れられたお茶に口を浸す。呼吸を整え、聞いてみた。
「その話は誰から聞いたの?」
「夕子だよ。祖母ちゃん」
ホッと溜息をつく。
そっか、祖母ちゃんの旦那さんになるんだもんな。知ってて当然だよな。
「光は何も知らないし、向こうも何も知らなかった。不動産屋は尚更だ。それなのに光はあの家を借りることにした。学生時代、家主さんから光とそっくりな子供が住んでた家だと聞かされたこともあったらしいけど、本当の親子だとは誰も思わないよ。宮子ちゃんともよく似てるって云われたらしいけど当時は全く知らないし、血は繋がっていたわけだから深く考えないようにしてたって。その話と夕子が光人さんから聞いていた話が繋がるなんて、神様も残酷なことするもんだよな」
そう云うと、卓袱台に置いてあった籠からチョコレートを一つ取りポイッと口に放り込んだ。
「あの手紙は親父が見つけたの?」
「正確には違う。あの家を取り壊すことになって光は手伝いに行ったんだ。家主さんが亡くなっていて、手紙自体はその跡取り息子って人が見つけたんだよ。後で聞いたら階段の隙間に埋めるように挟んであったらしいよ。取り壊しでもなければ絶対気付かなかったと光が云ってた」
あ。知ってる、その人。野木(のぎ)明石(あかし)さんだ。京都に行くといつも挨拶に行ってたし何度か泊めてもらったこともある。最後に親父と行った時も確か泊めてもらった。
どんな巡り合せで親父の手に届いたのか、不思議でならなかった手紙。あれさえなければ俺たちは今も家族だったんだろうか。
手紙。
“光”と署名のあった、あの手紙。あの署名がなければ、どうなっていたんだろう。
「親父はいつあれを読んだの」
という問いに、俺が小学六年の夏休みだったなと答えた親父。
半年間思い悩み誰にも云えずに苦しんだと。何年も忘れ去られていた古い手紙。どうしてそんな物が突然出てきたのかと、本当に読んでしまった自分を呪ったらしい。結局家を出る覚悟を決め、身辺整理を始めたと云った。秋の彼岸に二人で墓参に出かけ、それが親父との最後の旅行になった。本当の意味での最後の春の彼岸には両親だけで行ったから。
そして、その春、親父は家を出て行った。
翌日には警察に捜索願いを出し、みんなに迷惑をかけて捜してもらった。三日後、祖母ちゃんがみんなを集めてお礼をしたのを憶えている。俺は諦めきれなくて祖母ちゃんを責めてしまっていた。
「祖母ちゃん、どんな気持ちで捜すのを止めるって云ったんだろう」
「さあな。ただ、きっと光は帰ってこないから無駄だとは云ってたよ」
「少しは事情、知ってたの?」
「そりゃ、光と宮子ちゃんを結婚させたくらいだからな。でも、そこまで。真実は光が持って行った」
あれ?!
何か、今凄いこと云われた気がする。
「ちょっと待って。結婚させたってどういうこと?!」
「そのままさ」
「じゃ、二人は叔母と甥の関係だって解ってて結婚したの?」
「あゝ」
あれ、俺の勘違いかな。
「叔母と甥って結婚出来るの?」
「出来ないよ」
おじちゃんの言葉は、まるで悪魔の宣告だった。
刹那、心臓がバクバクし始めて、両腕で体を支えるのがやっとだった──。