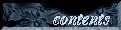『祭囃子』

第三章「春祭り」
№7
「マスター。美味しい珈琲を一杯」
始業式の日の夕方、六条亭である。
大きさこそないが店舗はカウンターと、四人がけのSETが六つ。ソファ等は薄い紫をメインに同系色でまとめられており、大袈裟には飾らずBGMはクラシック。居心地の良い雰囲気の店だった。
高校に近いこともあり、生徒たちもよく立ち寄るが必ずクラスの確認と決まった時間には帰宅するよう追い出してくれるので、父兄からも「ここなら」と許している場合が多い。他の教師も数名は常連である。
そんな中で、俺は何時しかカウンターの左端が定位置と決まっていた。
「おや。私の入れる珈琲はいつも美味しい筈ですが」
「ごめんなさい。そういう意味じゃなかったんですが」
六条亭に来るのは好きだ。
マスターと取りとめのない話をするのが好きだったし、暫くいると若菜が出てくる。こちらから話しかけなければ絶対に声をかけてはこないし、話しかけてもすぐ逃げ出してしまう。そんな若菜が好きだった。そんな関係ももう三年だ。
出された珈琲を少しだけ口にふくむ。うん、いつ飲んでもやっぱり美味い。
「マスター。俺が勘違いしてること、知って黙ってましたね」
いつもの世間話のように、何気なく口にした。
「先生、可愛いから。でも三年間も気付かないんだから、よっぽど人がいいんだとは思っていましたよ」
俺たちは気持ちよく笑った。
ちょうど、そこに若菜が手伝いに出てきた。店が混んでいることもあり、俺には軽く会釈をしただけで近寄ってはこない。
若菜は今までと全然変わらない。それなのに彼女の担任が自分だというだけで、俺の方が焦ってしまっている。
しかし、こいつが中学一年だったとは思わなかったなぁ。背も三年前にすでに今くらいはあったし髪も長かったから、てっきり高校生だと思いこんだんだ。よく考えれば中学生でない理由にはならない。なのに一度も年齢を聞くということをしなかった。
いや、若菜がなかなか打ち解けてくれなくて、そんなことどうでもよくなったのかもしれない。
「先生」
そんな物思いに耽っているとマスターから呼ばれた。
「はい」
注文の珈琲を入れる間、若菜がほんの一メートル先に立つ。
「先生ならいいですよ。若菜のこと、口説いてやって下さい」
「えっ?!」
そんな言葉を若菜だって聞いたのに、あいつときたら眉一つ動かさずトレーを運んでいく。俺、自信失くしそう。
「文句云う奴がいたら、私が許したって云ってやります」
そう云うとマスターはかっこよくウィンクをする。俺は言い返す言葉が見つからず、小さな溜息を一つつくと残っていた珈琲を飲み干した。
「この店、どうして六条亭っていうか知っていますか?」
唐突にマスターが聞いてきた。読んでいた小説をテーブルに置くと、俺は顔を上げる。
「いいえ」
「息子の名前は薫。娘たちの名前が月子と若菜。普通、国語の先生なら気付きませんか」
「俺、数学専門なんですが。ま、いいや。もしかして源氏物語」
薫に明子に若菜。風流な名をつけたものだ。
「正解。だから先生なら特別に許す」
二杯目の珈琲を出しながら、マスターは確かにそう云った。
「そこんとこ、よく分からないんですが」
「源氏物語の原作者は誰ですか?」
「紫式部」
あ…
流石に気付いた。子供の頃はよくからかわれたけれど、大人になったら誰も云わなくなったから忘れてた。
「やられました。でも、いちお教師なんで、ちょっと頑張ってみます」
俺の気持ちも立場も全部知ってるマスターは「それでいいんですか」と笑ったが、仕方ないだろうなぁ。そういや京都の彼も明石さんだ。何か関係あるんかな?
「桜祭り、やってますよ。今夜みんなで行くんです。先生も一緒にどうです?」
マスターからの誘いを、俺は心よく承知した。