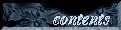第十三話 長隆
日々は穏やかに過ぎ、私は、三人の子の母となった。
未来によって知る歴史が確かに過ぎていると感じたのは、信長の傍若無人振りが殊更に伝わるようになってきたから。
文長は相変わらず、信長のすることを細かく知っていたけれど、いつしか、それは帰蝶が届ける文からの情報だと分かった。
だからといって、帰蝶の云うことを聞いてやるという感じではなく、安土の天守閣が完成し物見遊山に来いと云ってきた時も、文長は断わってしまった。
あれは残念だったな。
現代人としては、是非とも見てみたい安土の天守閣。
しかし二人目の子を宿していた私は、仁をも含めて猛反対にあった。
この時代、旅は簡単ではない。その上、身重では命の保障もままならなかった。
天正九年が明けた。
それが、どんな年にあたるのか。私には分からない。
楽しい日々、とはいえ本当に忙しい日々。
この時代、紙おむつなんてものはない。
私は、このおむつの洗濯と食事の支度に追われる毎日を送っている。
この時も、歩き始めたばかりの末の孝(こう)のおむつを替えていた。庭続きの縁側だ。二番目の子も年子の二歳、まだまだ目が離せない。
ふと、その子の声音が変わったことに気付いた。
「礼(れい)、どこ?」
私は、手を動かしながら視線を庭へと戻す。
声は聞こえている。
でも見えない。大急ぎでおむつを替えおわると、汚れ物も放り出し庭へ出た。
「礼!」
まだ、片言しか話すことは出来ない。誰と一緒にいるのかと不安になった。
「花穂様ですか」
突然、背中から掛けられた声を私は飛び上がるほど驚いて聞いた。
振り返ると、少年のような男の子が礼を抱いて立っていた。
誰、と聞こうと思った。思ったけれど、その後ろにいる人影に気付いた。
「文長」
どうりで礼が泣かない筈だ。
「こいつは長隆(ながたか)。私の友だ」
そう云った文長に対し、とんでもないと彼は恐れ入っている。
う〜ん、どんな関係?
私たちはふたりの子と共に、部屋へと上がると食事の支度を頼まれた。
四つになる上の緑(みどり)は、仁の許を離れない父親っ子だ。
私たちは文長の厚意により、今は一緒に暮らしている。食事も一緒、こうして文長の友達が訪ねてきても、それは変わらない。
ただ、不思議。
長隆を友だというわりには、文長の物言いは随分難しそう。
子を見ながらの話は、さぞ面倒だろうと思うのだけれど、長隆は全く気にもしていない。礼も孝も、よく懐いている。
きっと小さな兄弟がいるのね。
私は、そう思った。
やがて仁も戻ってきて、みんなで夕餉を囲んだ。
長隆の持ってきてくれた、何かの(ここは、あえて聞かないことだ)肉も美味しく戴いた。
夜、長隆と文長の姿が庭にあった。
「お戻り下さい。あの方に信長様を名乗ることは、もう無理だと存じます」
長隆の済んだ声は、扉を隔てていてもよく通った。
「もう少し任せてみよう。彼奴が信長だ。今更、俺が何を云っても聞かないと思うぞ」
文長の声もまた、低いながらもよく聞こえた。
「しかし、あの方は狂っておいでです。兄ですら、最近の信長様は分からないと申します。今なら、まだ間に合うかもしれません。少なくとも僧侶達の怒りを解くことができれば事態は大きく変わります」
その後、暫くは言葉が複雑で聞き取ることはできなかった。
しかし次の言葉を聞いた時、私の心臓は震え上がった。
「文長様が、真実信長様だと知れば、多くの家臣が納得する筈です。文長様なら比叡山を焼き討ちになどなさらない。延暦寺の方々も、今までのことは弟君のしたことと説明すれば分かって戴けるかもしれない。もう後がありません。どうぞ、信長様にお戻り下さい」
私は知らず知らずのうちに部屋を出ていた。
「文長・・」
私の小さな問いかけも、闇の中では充分に届く。
「花穂」
「あなたが信長なの?」
長隆は、すぐに私の足元に平伏した。
「花穂様にもお願い致す。信長様を我々に返して戴きたい」
「長隆、無駄だ。花穂は落ちてきた者だ。お前の泣き落としは効かないよ」
そうでしたか、と長隆は顔を上げた。
「長隆、教えて。文長の弟って、誰?」
「信長様の双子の弟君で在られます。お母上が犬畜生と、ご出産時捨て置かれた名もない弟君のことです」
双子? 信長が?
「文長、ほんとなの?」
「史実は、後の世を作った者の歴史だ。織田は滅びるのだろう。だから私が双子だということなど残っていないのさ」
文長は、そう云うと夜空を見上げる。現代では考えられない、満天の星空。月の形が薄くとも、月明かりと星は夜を照らす。
「私に語った信長の歴史の中で、文長が信長として生きた時間もあったの?」
「勿論。花穂には、少しでも知って欲しくて根掘り葉掘り聞いたよな」
あ・・。
「まむしの処に乗り込んだ」
文長が嬉しそうに笑った。
仁も、飲まないか、と酒を片手に出てきた。
「仁も知ってたの」
ごめん、と云った仁の言葉の裏に事の重大さが隠れていた。
「帰蝶が、信長と不仲だというのは間違いね。彼女は本物の信長にだけ尽くした。まむしの娘は、いつ真実を知ったの」
長隆が、云う。
「輿入れ道中で」
凄い。
「どうして分かったの?」
「信長は腰抜けだと、帰ろうとなさったそうです。道々の様子や警護、また緊張感も父道三殿から聞いた信長の所領ではないと。このような男は影武者に違いない、と云い放ったそうです。遠くから様子を伺っていた文長様が、慌てて取り繕うとなさると」
と、そこで文長が言葉を奪う。
「お前が本物の信長か、と見抜かれたんだ」
文長の口調は、何だか楽しそうだった。何かを思い出してでもいるかのように。
「長隆。お前の名は何と云うの?」
すると長隆は文長を見る。文長が黙って頷くと、彼も決心したように答える。
「森坊丸長隆にござります」
あの、蘭丸の弟だった。
信長、織田信長。
あの史上、最も有名で悲劇の武将が、今、目の前に立っていた――。