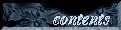第十四話 本能寺
次に長隆がやって来たのは、翌天正十年のことだった。
「信長様が、朝廷と対立する道を選ばれました」
流石に文長も、耳を疑った。
蘭丸の話によると、と前置きした形で長隆は語った。
「どのような官位も望み通りに与える、という朝廷に対しご返答なさらず」
と。
信長は、以前にも官位を辞退したという経緯もあって、これで朝廷側は完全に反旗を翻されたと感じただろうと。
それは何を意味するのか。
長くこの土地で暮らす私にも、もう理解できる。
何かに書いてあった。信長は強く成り過ぎて、ノイローゼになっていたんじゃないかと。それと、本能寺の変直前には戦意を失っていたとも書いてあったっけ。
長隆の話だと、このところの信長は蘭丸だけを手元に置いて、他の誰も寄せ付けないらしい。
長隆だけは、連絡係として針小棒大なく事実のみを伝えるという理由で重宝されているというが、役目が終われば追い出される。長く務めた家臣も意味もなく放逐される。
あとは転落するだけだと、文長が呟いた。
「じゃ、どうして助けてあげないの? 弟、なんでしょ」
文長が私を見た。
「歴史なんて、変わったっていい。今、文長が泣くくらいなら、私の知る歴史を教えてあげる。だから助けに行ったらいい」
「花穂」
文長が、呼びながら私を抱きしめた。
幾度も幾度も私の名を呼びながら、抱きしめる。どうやら泣いているみたい。
「花穂なら、そう云うと思った」
仁が、云う。
「文長。本能寺には近づくな。俺にはそれだけしか云えない。後はお前が考えろ」
顔をあげる文長に、仁は続ける。
「そこに近づくことがなければ、もしかしたら何かが変わるかもしれない」
「本能寺・・」
「そうだ。帰蝶を嫁にしたのは、お前だろ。彼奴のことも考えてやれ。側室にデカイ顔されて、それでも黙っているのは文長を守るためだ。あの帰蝶がそこまでするのは、この世でたった一人文長のためだけだ」
それを聞いた文長がゆっくりと離れていく。
「行くよ。史実は関係ない。弟と愛しい女を助けてくる」
そうこなくっちゃ。私は、文長の頬にキスをする。
「あ、文長が照れてる〜」
「仁、お前、こんなことさせていいのか」
「文長になら、許す!」
莫迦、と言葉にする文長の瞳は、うっすらと潤んでいる。
本能寺。
すべての発端と謎をはらむ場所。
でも仁は、明智光秀の名を口には出さなかった。
‘敵は本能寺にあり’
あのクーデターの真実は、どこにあるんだろう。
「仁」
「ん?」
子供たちが寝息をたてる間に、ふたりで相対した。
「光秀の軍は信長の命令で集められた。だから信長は、ぎりぎりまで光秀の裏切りに気付かなかった。蘭丸ですら、死んだ。裏切りは光秀じゃないかもしれない」
仁は私の頭を、まるで小さな子供にするようにぐりぐりと撫でた。
「大変よく出来ました。住んで初めて知る事実だな。いや、気配の方が正しいかな。あの歴史は、どこか変だ。誰かの策略に乗せられるのだけは、ごめんだからな。たった一つの真実は、本能寺で何かがあったということだけだ」
仁は、そう云って遠くを見るような目をしてみせた。
そうだ。
すべては本能寺で始まった。
秀吉の天下統一も、徳川による豊臣家滅亡も、その後続く徳川政権も、すべては本能寺が幕開けだった。
文長は、何を考えるだろう。彼は歴史を変えることができるのだろうか。